
社長さんの相談室
President's Consultation Room
経営者のためのサービスです。
社長さんからの個人相談はもとより、経営陣と「未来に照準を合わせた御社ならではのビジョン作成」するためのプロセスを伴走します。それを社員の方々にも「自分の会社を誇りに思える生きがい」にしていく実践的ワークショップなど、御社のご事情にふさわしい、オーダーメイドのきめ細かいサービス内容です。

経営者のためのサービスです。
社長さんからの個人相談はもとより、経営陣と「未来に照準を合わせた御社ならではのビジョン作成」するためのプロセスを伴走します。それを社員の方々にも「自分の会社を誇りに思える生きがい」にしていく実践的ワークショップなど、御社のご事情にふさわしい、オーダーメイドのきめ細かいサービス内容です。

経営者ではない方にも、どんな立場の方にでも有効なサービスで、単発でも継続的にもご利用いただけるZoomの対面コーチングです。
企業経営者の方、学校の先生、NPOや諸団体など「組織運営」に関わっている方はもちろんのこと、仕事と家庭の両立を図っている方々にも最適です。

経営者ではない方にも、どんな立場の方にも有効なサービスです。面談ではなく、メールでコーチングを行なっています。メールに書くことで、脳が整理・編集され、既成概念にとらわれなくなるからです。
メールコーチングをご体験者からは「答えが返ってくる日記」「世界でひとつの自分だけの教科書」と評価をいただいています。

どんな立場の方にも有効な「サードアンサーコーチ」の養成を行なっています。
サードアンサーは、メールコーチングや、ライブセッションの中で、あなた自身が体験できると同時に、ご自身も身につけて、仕事としても行うことができるスキルが身につきます。「自他実現講座」のアドバンスですが、社内コーチの養成にも応用できます。
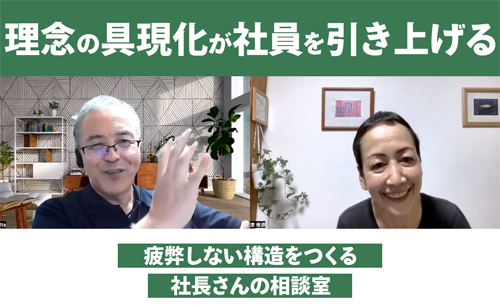

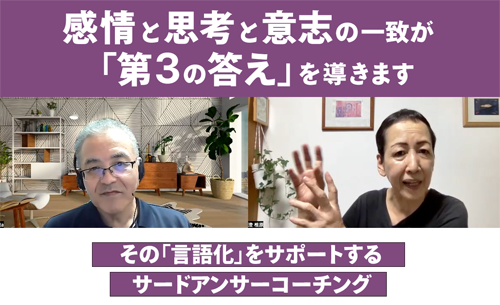

まずはお気軽に体験フォームをお送りください